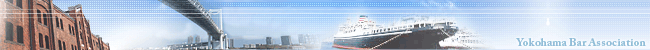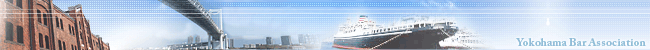| 会員 澤田 久代 |
| 何故今事業承継なのか? |
| 中小企業は、我が国の企業数全体の90%を占めるとともに、雇用の面でも約70%を支えていると言われている。また、中小企業は、そのほとんどがオーナー企業である。 |
| 今日、この中小企業の経営者の高齢化が進んでおり、今後10年程度の間に、経営者の引退又は死亡による交代という事態に直面することが避けられない状況にあると言われている。しかし、事業承継の必要性・困難性を十分に認識しその準備をしている会社は少なく、このままでは、経営の交代が進まず、日本の経済そのものにも打撃を与えることが予測されるに至っている。 |
| 事業承継問題は、事前に十分な準備をしておくことが必要とされるが、他方、この問題は、経営の交代という問題と直面することから、経営者本人はもちろん、その家族や従業員たちが、正面から取り上げて検討することには抵抗がある問題といえる。 |
| そこで、事業承継問題の普及・啓発を図ることの必要性がうたわれ、国の政策として、事業承継のための専門家のネットワーク構築や事業承継支援センターなどが各地に設置されるに至っている。 |
| |
| 事業承継対策の流れ |
| 事業承継対策の流れとしては、(1)現状の把握(2)後継者の決定(3)事業承継計画の作成・実施となる。 |
| 現状の把握としては、会社の状況(資産・収支の状況、役員構成、持株比率等)、経営者の個人資産の内容(自社株、事業用資産の内容、価格、換価性等)、後継者候補等を把握することが最低限必要となる。 |
| また、後継者を決定するにあたっては、親族(相続人)内なのか(親族内承継)、そうでないのか(親族外承継)、また、親族外の場合には、企業内の人材に承継させるのか、第三者にするのかを検討する必要がある。 |
| |
| 法律専門家としての関与 |
| 事業承継という観点からは、自社株や事業用資産を後継者と決めた人に対していかに承継させるかが決め手となる。 |
| 親族内での承継であれば、相続に絡む法的紛争をいかに未然に防止できるかに力を注ぐこととなるであろうし、相続税対策も必須の課題となるので、税理士との連携等も必要となろう。また、株式を生前に贈与してしまい経営から排除されてしまうことへの経営者の不安を取り除くという観点からは種類株式の活用等も検討する必要があるだろう。 |
| 親族外承継の場合には、どのような方法で譲渡するのが適切か(合併?株式売却?株式交換?等)等がまず検討されることとなろう。 |
| いずれの場合であっても、対策を検討し始めてから実施するまでには、相当な期間が必要である。かかる時間の必要性について、経営者に認識してもらうことこそ最重要課題といってもいいかもしれない。 |
| 今般、事業承継対策の一環として、遺留分減殺請求に関して民法の特例を設けることが定められた外、承継時の金融支援、相続税の納付に関する猶予制度等の法整備もなされた(経営承継円滑化法)。自社株の生前贈与などをする場合には、かかる特例の利用も視野にいれてみてはどうだろうか。 |