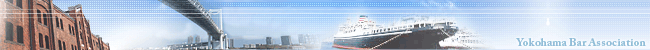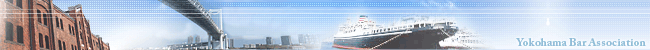| 日弁連交通事故相談センター 委員 三浦 靖彦 |
新年度より相談枠拡充
|
交通事故により脳に損傷を受けて意識障害が続いた場合、その後一見回復したように見えても、人格変化が生じたり、会話がかみ合わず感情の起伏が激しくなったり、物忘れが頻発し以前はできていたことができなくなったりする症状が発生することがある。これが高次脳機能障害である。
|
| 平成13年より、自賠責保険の後遺障害認定において高次脳機能障害認定システムが開始された。これを受け、財団法人日弁連交通事故相談センターでは、同年4月から交通事故に基づく高次脳機能障害を専門的に扱う無料法律相談を開始した。 |
同センターの神奈川県支部では一昨年よりプロジェクトチーム(PT)を立ち上げて検討を始め、昨年6月から、毎月第2水曜日に1枠45分で4枠の「高次脳機能障害相談」を、当会会館内で行っている。
|
昨年12月現在、神奈川県支部での相談件数は、6月2件、7月2件、8月1件、9月0件、10月1件、11月0件、12月2件となっている。
|
一般交通事故相談に比べて相談件数が少ない理由のひとつとして、高次脳機能障害であることは分かっているが、それに対応する法律相談があることを知らないことが考えられる。
|
| そこで、PTでは、ちらしを作成すると共に、神奈川県総合リハビリテーションセンター(RC)や横浜市総合RC、川崎市北部RC等の専門医療機関と連携をとることより、高次脳機能障害を負った被害者への広報に努めている。 |
また、本年4月からは、相談日を毎月第2水曜日に加え第4水曜日にも設けることとなり、相談の機会を増やすことが決定している。
|
|
| しかし、未だ被害者に十分法律相談の存在が知られているとは言えない状況であり、さらに、症状が出ていながら、それが高次脳機能障害に該当することに気づいていない被害者の救済についても課題が残っている。 |
交通事故後に、怒りっぽく乱暴な言動が目立つようになった、集中力が下がり、同じ失敗をすることが多くなった、物忘れが激しくなったり、たびたび計算ミスをするようになった、等のことがあった場合、それは高次脳機能障害かもしれない。
|
被害者本人のみならず、その家族や相談を受けた関係者が、本記事をきっかけに高次脳機能障害の可能性に気づいて、高次脳機能障害相談の積極的利用をしてもらえれば幸甚である。
|

|
| 昨年12月4日(土)、戸塚にある男女共同参画センター横浜で、全面的な国選付添人制度の実現を目指すシンポジウム「子どもたちにも弁護士を!!〜家庭裁判所の少年審判を受けた元少年の声を聞く〜」 が開催され、約100名が参加した。 |
| 成人の事件については、被疑者国選対象事件の拡大により、被疑者・ 被告人段階を通じて、大部分の事件で国選弁護人が選任されるようになった。 |
| しかし、少年事件については、一部の重大事件に限って国選付添人制度が存在するだけで、その他の多くの事件では、付添人がつかないか、付添人がつく場合でもその費用は個々の弁護士から徴収されている特別会費を財源とした援助制度で賄われているケースがほとんどである。 |
| そこで、少年にも成人と同じように審判段階の付添人を国費でつけられるように、国選付添人の対象範囲の拡大を求めるというのが今回のシンポの目的であった。 |
| 開会後、まず、付添人の活動を紹介するDVD「オレってこれからどうなっちゃうの?〜弁護士山村亜紀の付添人日記〜」を上映した。このDVDは出演者全員が当会子どもの権利委員会の委員で、付添人の活動をわかりやすく紹介するものである。 |
| 次いで、ジャーナリストの江川紹子氏が、少年審判を受けたことがある元少年3名と、自らの子どもが少年審判を受けたことがある保護者1名へのインタビューを行い、大変貴重な生の声を聴くことができた。 |
| さらに、元少年と保護者に行った事前アンケートの結果報告がなされ、家庭裁判所調査官および自立援助ホームのホーム長からの会場発言の後、江川氏から、「少年に対して親ではない大人としての付添人が働きかけることにより、少年自身が事件や自分自身の生き方を考えるきっかけとなっており、こうした付添人の役割を広く社会に伝えていかなければならない」というまとめがあった。付添人活動の意義について再認識できた中身の濃いシンポであった。 |
| (子どもの権利委員会 委員長 高橋 温) |